
登場人物紹介
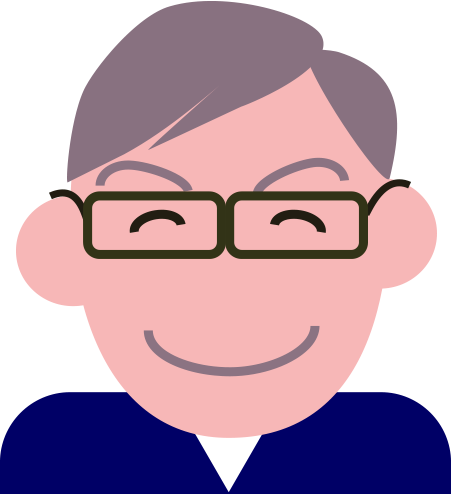
校長先生
特別活動のことなら、
なんでも来い!
知る人ぞ知る、伝説の特別活動名人。

ユメ先生
憧れの小学校教諭になったばかり。
元気とやる気でいっぱいの新人先生。
「子供が話しに来たんです」

お、ユメ先生。張り切っていますね!
何かいいことでもありましたか?

はい!
実は、子供が話しに来たんです。
「先生、○○さんが転校するなら、
みんなでお別れ会をしたらどうですか。」って。

おお、なるほど。
子供からの提案は嬉しいですね。

そうなんです!
それで・・・
校長先生からの挑戦状!
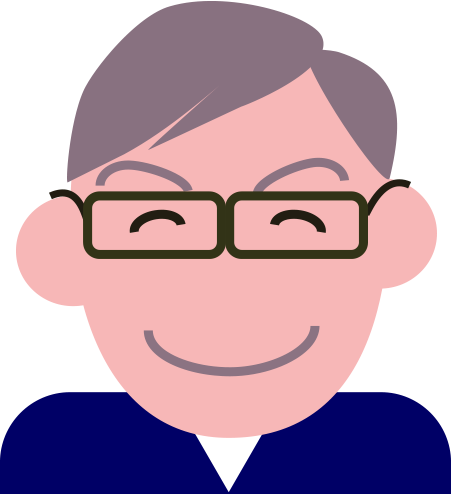
では、ここで問題です!
あなたがユメ先生だったら、この子供の意見をどのように取り上げますか?取り上げ方にはいくつかの方法が考えられます。
たとえば、
- 時間や場所、何をするかについての計画を先生が立て、先生の司会進行の下で、子供たちに「お別れの会」をさせる。
- 先生が決めなければならないことと、子供たちが決めることとを分けて、後者については、子供たちが話し合って決める。みんなで決めたことを分担し、準備をし、「お別れの会」を子供たちの司会進行で実施する。
- 「お別れの会」を実施するために、その計画などをする子供たちを募り、子供に任せて「お別れ会」を行わせる。
あなたがこの子供の担任だったら、どの方法を選択し、子供に対してどのように助言しますか?また、それはどうしてでしょうか?
「学級会としてはどうか?」という視点から考えてみてください。
解説

それでは、解説です。
「学級会」としては、2の方法が適切であると考えられます。
また、子供に対する助言としては、次のようなものが考えられると思います。
「○○さんのお別れ会ですね。学級会の議題として出してみたらどうですか。
〇〇さんのお別れ会をどうして行いたいのかという理由も伝えられるようにしておくといいですね」
子供たちが、自らの学級生活から「みんなでしてみたいこと」「みんなで決めておきたいこと」「みんなで作り上げたもの」などの問題に気付き、その問題から自分たちで解決できる問題を選び、学級会の議題とし、みんなで話し合い、その問題のよりよい解決方法を決め、自分たちで分担した役割ごとの計画、準備のもと、みんなで実践し、その実践を振り返る学習過程がある学びが「学級会」です。
そして、大前提として大切なことは、学級会が時間割に位置付けられている授業であるという点です。
授業ですから、担任の適切な指導の下での活動でなくてはなりません。
つまり、担任の指図に従って活動するものでも、子供に丸投げする活動でも、ないのです。
以上のことから、「学級会」としては、2の方法が適切であると考えられるのです。







校長先生!
聞いてくださいっ!!