未来予想と、新学習指導要領の目指すもの
講演終了後、天笠茂座長からは、次のようなコメントがありました。
「未来予想と、新学習指導要領の目指すもの、令和答申がかなり一致していると感じた。
どのような未来になるかの分岐点が、ここ数年のうちにあるという重要な示唆もあった。
学習指導要領を検討するとなると、内容も視野も限定されがちだが、広い視野で多面的多角的にとらえる問題提起としても聞かせていただいた。
答申や学習指導要領では、これから向かう社会として「デジタル社会」を提起しており、そこに向けて着々と準備しているところだが、超長期的という視野から、さらにその先に向かう社会を意識しながら議論していく必要性を感じた。
戦後日本は、もてる資源を東京に集中させて国全体を引き上げていくという手法をとっていたが、次の社会は地方分散社会という提議もあった。
それぞれの学校の在り方と絡めて捉えていくきっかけともなる、新しいご示唆をいただいたと思う。」
また、上智大学の奈須委員からは、
「現在、日本で地方に行こうとすると、自分の地元しか選択肢がないことが多いが、地域創生がうまくいっているところは、外から来た人が活躍できる社会が築けているところである。それができるような社会を作る、担い手である人を作る点については、教育の果たすべき役割が大きい。
地方分散型が成立するためには、「しがらみ」ではない地方の在り方が大事であり、新しい人が入ることで、町自体がどんどん変わっていける風通しの良さが必要となる。変革を実現できるのは、しがらみのない外から来た人である。いまICTを使ってやろうとしているのは、それを学校の中で体験してもらうことであり、トランスフォーマル=変革的な教育ということである」
という指摘がありました。
関連リンク

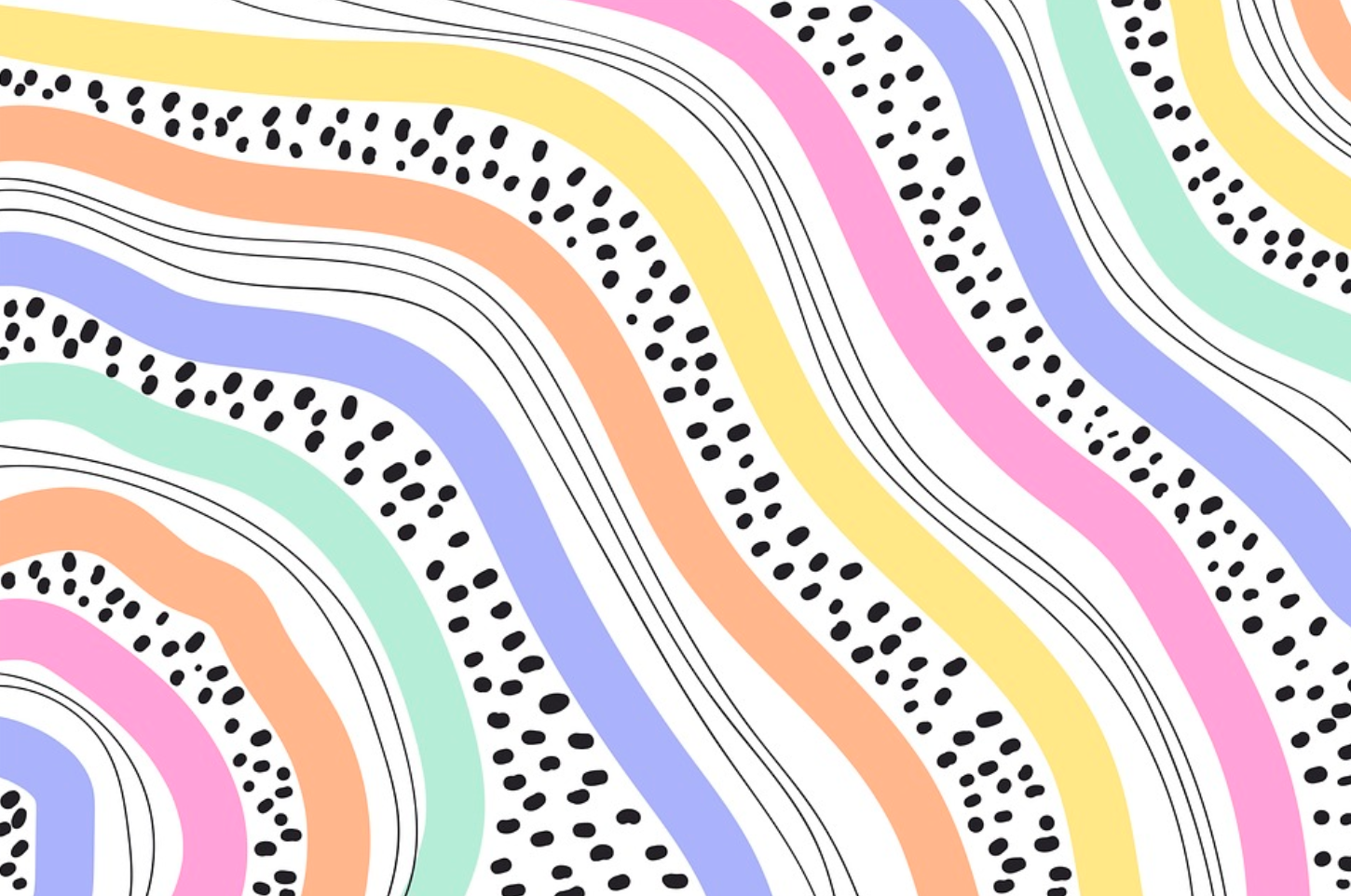






京都大学 人と社会の未来研究院
https://ifohs.kyoto-u.ac.jp/
今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会(第2回)会議資料https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/184/siryo/mext_00001.html