
小学校時代の思い出というテーマでアンケート取ると、クラブ活動や学校行事が多く上がるんですよ。(注1)
そういったところにも教育的意義が表れていると思うんです。
また一方で、先生方からも、特別活動がすごく教師としてのやりがいにつながっているというお話をよく伺うんですよ。
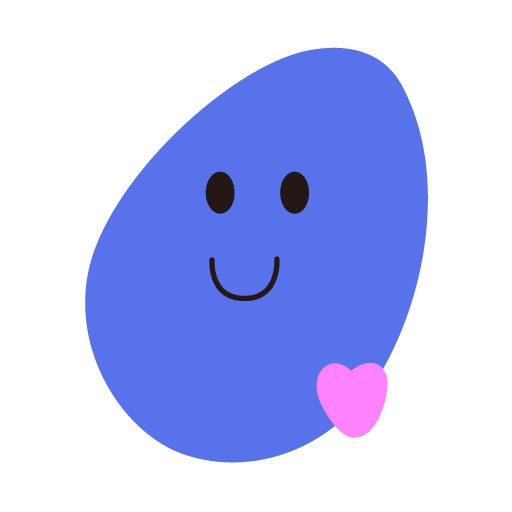
おお!そうなんですか?

はい。
たとえば、学級会の話し合いがうまくいって何か決められたときや、学校行事で、皆がしっかりめあてをもって達成できたとき、それから、学級が一団となって何かやったとき。
「教師になってやりたかったことって、これだな!」と思ったという先生方、たくさんいらっしゃるんです。
自分のイメージしてた小学校の先生ってこれだったって。
だから、そういう意味でも、「本来の」という捉え方があっても良いのではないのかなと思うんですよね、やっぱり。
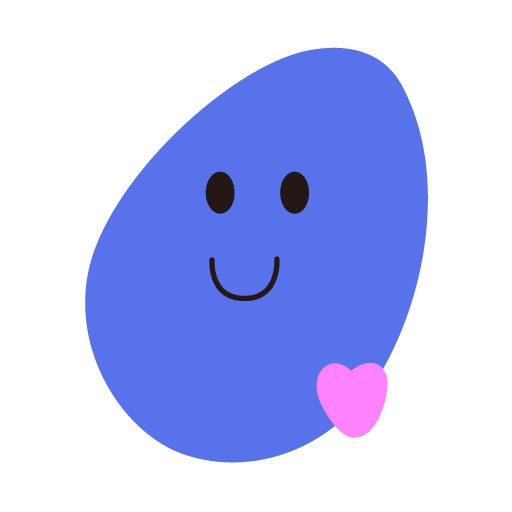
そういう学級にいれば、勉強も楽しくなるような気がします。

実際、今回の学習指導要領を検討する中での資料として挙げられていた事例なんですが、いわゆる荒れていた学校で、学級活動をしっかりやったら学習の成績も上がったというような結果も出ているのだそうですよ!(注2)
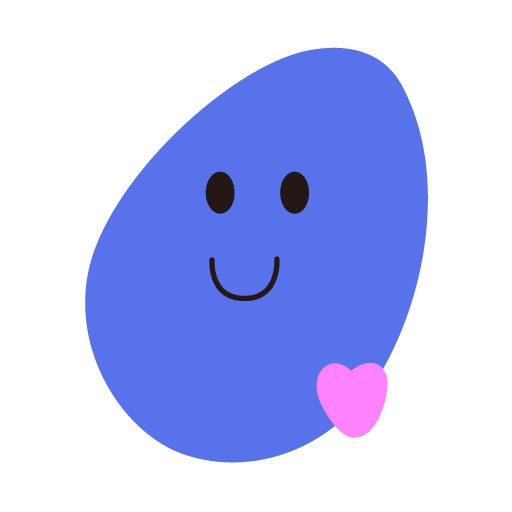
わあ!やっぱり!
でも、それはそうですよね〜
大人だって、友達もいない、居心地の悪いところで勉強したって、身に付かないわけですし。

安心感がないと学習効率も非常に下がってしまうわけですが、その安心感を生み出す、受容的な学級風土というものは、みんなで何かを作ったりみんなで何かを決めたりという、学級活動の「話し合い」活動を通して育まれる部分が大きいと思います。
道徳もまた、学級風土、学級経営とつながっていて、学級風土がちゃんと醸成されてると、みんなで思いを伝えやすいっていうようなことがあるそうなんですね。
国語や算数の授業で、いきなり「間違ってもいいよ」とか「発言していいんだよ」「間違ってもいいんだよ」と言ったって、やっぱりなかなか間違えられないと思うんです。
でも、特別活動や道徳だったら、自分の考えをどんどん言っても大丈夫なんです。
多少おかしなことを言ってしまったとしても、それは間違いじゃなくて、それをみんなでまた考えて、より良い考えにしていこうという場ですから。
そうやって醸成された受容的な雰囲気、学級風土っていうのが、教科学習の場でも「間違っても大丈夫」という雰囲気づくりや、友達同士で教え合う学習とか、そういったものにつながっていくんじゃないかなと思っています。
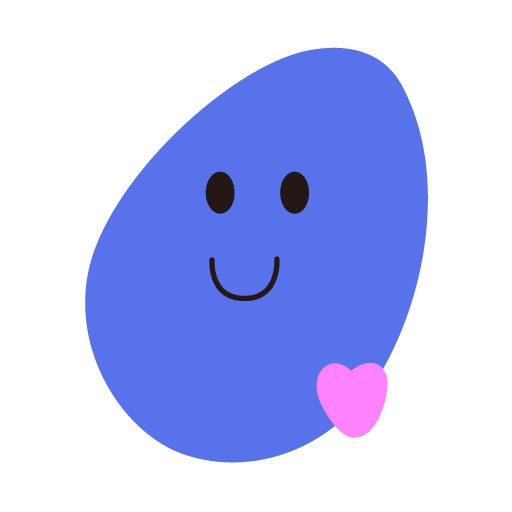
今のお話から、受容的な雰囲気の学級で、道徳と特別活動が両輪として働いているイメージがわきました。
そうか!だから「道徳と特別活動」なんですね。

つい先日のインタビューでも、先生が学級経営をしっかりされていて、学級をしっかり見ていると、自然とその学級の子供たちに対応した学習指導案ができて、子供たちの実態に合った授業ができるというお話が出たところなんです。
特別活動で耕した学級風土の上で、特別の教科 道徳をやることで、さらに心が耕され、成長するという感じで、まさに両輪なんですね。








なるほど!
確かに、大人になってもずっと覚えている、学校時代の思い出って、特別活動のことが多いですね。