自己指導能力を育む学級活動
学級活動は児童生徒が一番身近な所属集団である学級を単位として、全学年において行われており、教育課程に年間35時間(小学校1年生は34時間)位置付けられた活動である。
特別活動の基礎となる活動であるとともに、小学校第1学年から毎週活動の機会がある。
児童生徒にとって所属意識の強い集団である学級を、自分たちの力で運営したり、よりよい人間関係を築いたりする。個性や自己の能力を発揮し合いながら生きることの大切さを学ぶ学級活動には、生徒指導と関連を図ることができる機会が多い。
自ら考え、判断し、行動に移す自己指導能力の育成には、児童生徒が自主的・主体的に活動する場が必要である。
学級活動は活動を通して「自主性」と「主体性」を育んでいく。
ここでは、「自主性」を、自分の役割や、やらなければならないことを理解し、人から促されなくても自ら進んで実践・行動できる力、また「主体性」を、課題解決のための方法を考え実践・行動できる力と考えたい。
具体的な活動で考えてみると、学級活動(3)イ「社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解」において、当番活動で決まった役割を責任もって果たしたり、学校や学級のルールを守り日常生活を適正に過ごしたりする力は、「自主的」な力と言える。
教室でよく目にする当番表や学校のきまりの表示は、いわば児童生徒が人から言われなくても自分の役割や、集団生活を円滑に行うために定められたルールを確認できる「自主性」を育てるアイテムである。
また、学級の目標を達成するために、学級においてどのような方法で自らの力を発揮するか、その行動を意思決定し、実践を重ねていく力は「主体的」な力と言える。
これらの力が育つことで、新型コロナへの対応において自分や周りの人を守るために手洗いやうがいといった、決められた行動様式を「自主的」に行ったり、高温のときに体温調節をするためにマスクを外す際には人と十分な距離をとり、人のいない方を向くなど「主体的」に解決の方法を考え行動したりすることにつながるのである。
さらに、自己指導能力の育成を目指す生徒指導が、学業指導や適応指導、進路指導、社会性指導、道徳性指導、保健に関する指導、安全に関する指導、余暇指導などに分けて考え、計画されることがある。このことを学級活動の内容との関連を考えると、次のように考えることができる。
学級活動⑵「日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全」
- ア 基本的な生活習慣の形成〔学業・適応・保健・安全・余暇〕
- イ よりよい人間関係の形成〔適応・社会性・道徳性〕
- ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成〔保健・安全・余暇〕
- エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成〔適応・保健〕
学級活動(3)「一人一人のキャリア形成と自己実現」
- ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成〔学業・進路・社会性・道徳性〕
- イ 社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解〔学業・進路・社会性・道徳性〕
- ウ 主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用〔学業〕
※〔〕内は生徒指導との関連例
学級活動の内容が、個々の児童の自己指導能力の育成を目指した指導が中心的に行われる場と言える。
効果的な学級活動の実施
これまで述べてきたように、新型コロナの状況は児童にとって学校行事をはじめ、多くの特別活動の場を奪っていることは事実である。
しかし、このような状況の中だからこそ、安全を守り、児童一人一人が自らの力を発揮するための自己指導能力の育成に特別活動がどのように関わっているかを再確認することができる。
その上で休校措置等に伴い十分な時間や環境がない中、効果的に特別活動を実施していくためには、時数として位置付けられた学級活動の時間だけではなく、朝の会や帰りの会も含めて計画を考えていく必要がある。
また、必要に応じて養護教諭や関係機関といった学校内外の教育資源を活用することも有効である。
最後に、新型コロナによりこれまでとは違う教育活動に現場の先生方が向かい合う姿は、児童にとってまさに身近で見る課題解決の姿であろう。
課題を解決するための工夫や情熱に触れることは、これから自己指導能力を身に付けていく児童にとってよい経験である。
困難に立ち向かい教育活動を進めている、全ての現場の先生方に敬意を表したい。

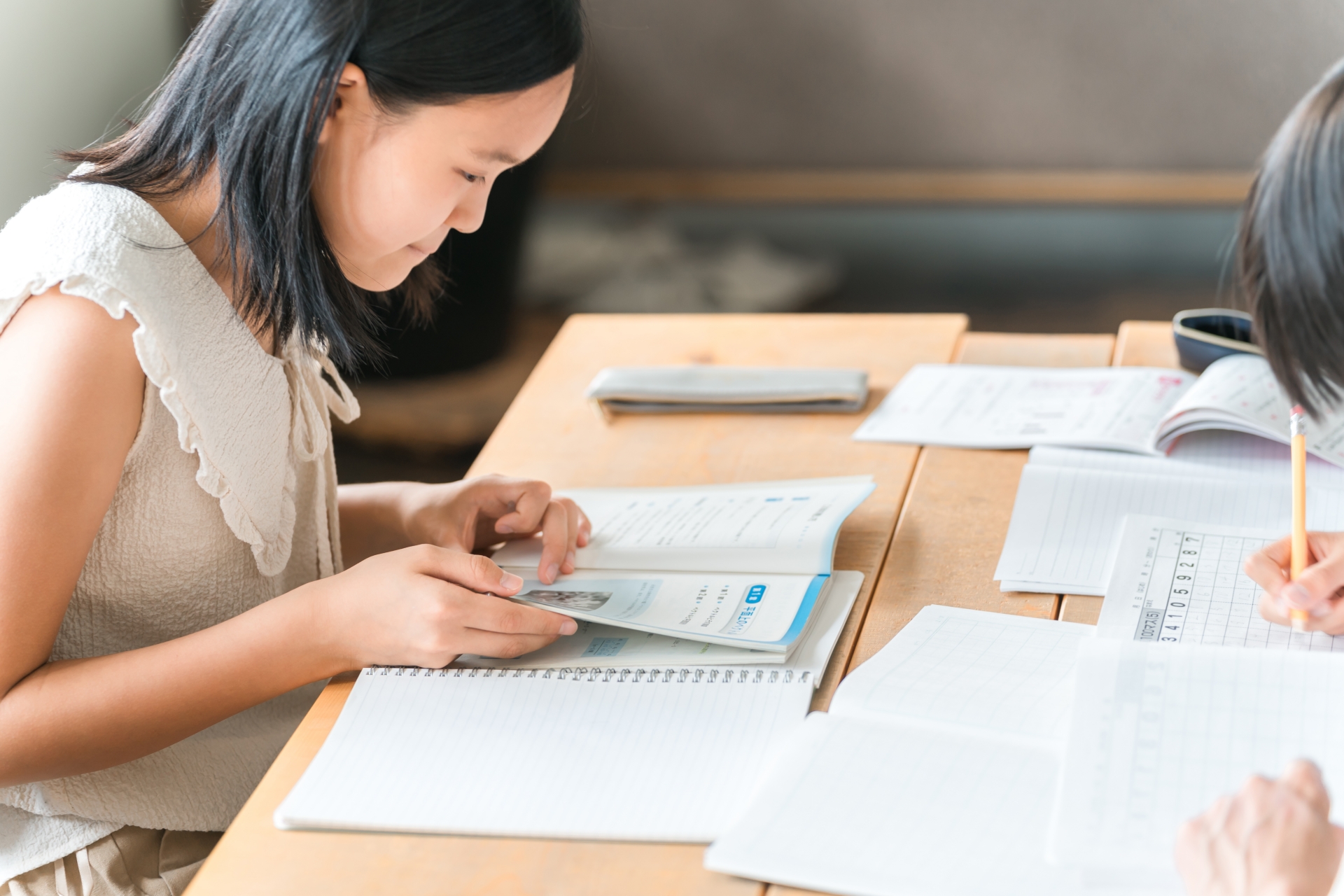






※本記事は月刊誌「道徳と特別活動」2020年9月号
(特集:児童の自己指導能力を高める学級活動 ― 特別活動 基本と応用vol.2 ―)からの転載です。
▶︎「道徳と特別活動」について詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281702462/